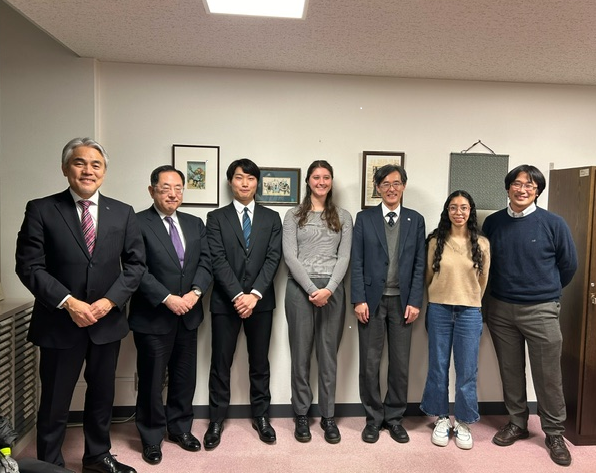学生の活躍
世界中で活躍する所属生・修了生の声
修士からでも遅くない!初級から上級までを修了して
工学院 システム制御コース(2020年度修了) 山本 大起
グローバル理工人育成コースに所属したきっかけ
英語力を上げたいと思ったのが最初のきっかけです。グローバル理工人育成コースでは、英会話レッスンや英語試験を無料で受けられる支援が定期的にあり、本コースに所属している学生から優先して受けられます。所属した当時はドイツでの海外インターンから帰国した直後だったので、英語力を落とさないためにも英語を話す機会に飢えていました。
私の場合、海外経験を積んだ後に本コースに所属した形になるのですが、留学のためのサポートなども充実しているため、”グローバル”という言葉が気になったタイミングでとりあえず所属してしまう方が良かったと今では感じています。
忙しい中、なぜ活動を進めようと思ったのか?
「グローバル理工人育成コース」という名前は学士の頃からうっすら聞いたことはあったものの、なんとなく所属はしていませんでした。
その後、前述の流れで修士課程の途中から本コースに所属したものの、修了を目指していたというよりは何かいい機会に巡り合えればという軽い気持ちでした。
所属後、コース対象科目の一覧を眺めてみると、半年間の海外インターンを経て国際意識が存分に高まっていた私にとっては興味深い科目ばかりでした。それに加えて海外経験3ヶ月以上という比重が大きめの修了要件を既に達成していることもあり、せっかくだったら上級の修了まで目指してみようかと思うようになりました。
振り返ると、研究や通常の授業が忙しくても、その合間に息抜きのように講義を受け進められたと思っています。講義は英語を話す機会にもなるため、私の最初の動機にぴったりでした。特に今年は新型コロナウイルスの影響で講義がオンラインであったこともあり、通常よりも気軽に受け進められたように思います。
所属しようか考えている皆さんへ
私は修士からグローバル理工人育成コースに所属したため、まずは学士向けとされる初級・中級を修了するところから始まりました。ときには学士1年生などと一緒に「グローバル理工人概論」を受講したりもしましたが、修士の私にとっても学びは多かったです。修士向けの講義に関しても多国籍チームで働く際の難しさや理想のリーダー像について留学生とディスカッションをしたりして、より実践的なスキルが身につきました。少人数のディスカッション形式で進んでいく授業スタイルは刺激的で、専門性の高い授業や研究のストレスをうまく和らげることができていたと思っています。
修士課程の2年間のうち、半年間をドイツの海外インターンに使い、その後の1ヶ月を欧州旅行に使い、残りの短い期間で研究や就職活動、通常の講義の履修、そして初級・中級・上級のコース対象科目の履修をしました。
一部の方からは、研究がそんなに忙しくなかったんじゃないかと思われるかもしれませんが、修士論文発表会で最優秀賞をいただいたくらいには研究の方も頑張ってきたつもりです。
ここで伝えたいことは、学部の時にはサークルやバイトで忙しいからとなんとなく所属していなかった私のような人も、今から所属するので全く遅くないということです。講義を受ける時間は研究の合間にも作ることができますし、仮に修了を目指さなくても何かしらの挑戦をひとつするだけで大きな価値があると思っています。
ドイツ・フランクフルトでの経験
私はドイツ・フランクフルト地区で半年間インターンに参加し、電気自動車の研究に携わりました。業務は全て英語で行われて、ヨーロッパを中心に世界各国のエンジニアが集まっているような環境でした。報酬の出るインターンだったので、経済的にも無理なく長期の海外経験が積めたのはかなり恵まれていたと感じています。
英会話の練習もほとんどせずにドイツに飛んだため、仕事面で様々な苦労をしたことは言うまでもありませんが、私生活の方でも初めから困難の連続でした。
海外での部屋探しは勝手がわからず、オーナーからの信頼も得づらいので難しいです。特にドイツ・フランクフルト周辺が人気地区だからということもあり、私の部屋探しはうまくいきませんでした。日本からネットを通じてなんとか見つけたルームメイトに裏切られ(空港に迎えにきてくれる約束をしていた)、初日に空港でホームレスが決定し、その後見つけた部屋はライトもキッチンも寝具もなく、壁塗りからの本格的なリフォームを自力ですることになる、という感じでした。
最初の数日間は慣れない英語での仕事から帰った後に、部屋のリフォームをして、日が暮れたらライトもない部屋で涙を流しながら寝ていました(笑)
しかし結局のところ今ではいい思い出ばかりで、ビールは安くて美味い、週末には陸続きの美しい隣国に旅行し放題、そしていろんな国の人たちとも出会えました。(ドイツを留学先の選択肢のひとつとしておすすめしておきます。)
海外では基本的に誰も助けてくれません。どうしていいかもわからない地でなんとか生き延びるためには結局何か行動をするしかないので、行動力や積極性は自然と身につきました。これらは今後の人生でも必ず活きていくと思っています。

左)壁塗りが終了したとき(ライトはまだない)・右)念願のマットレスが届いたとき
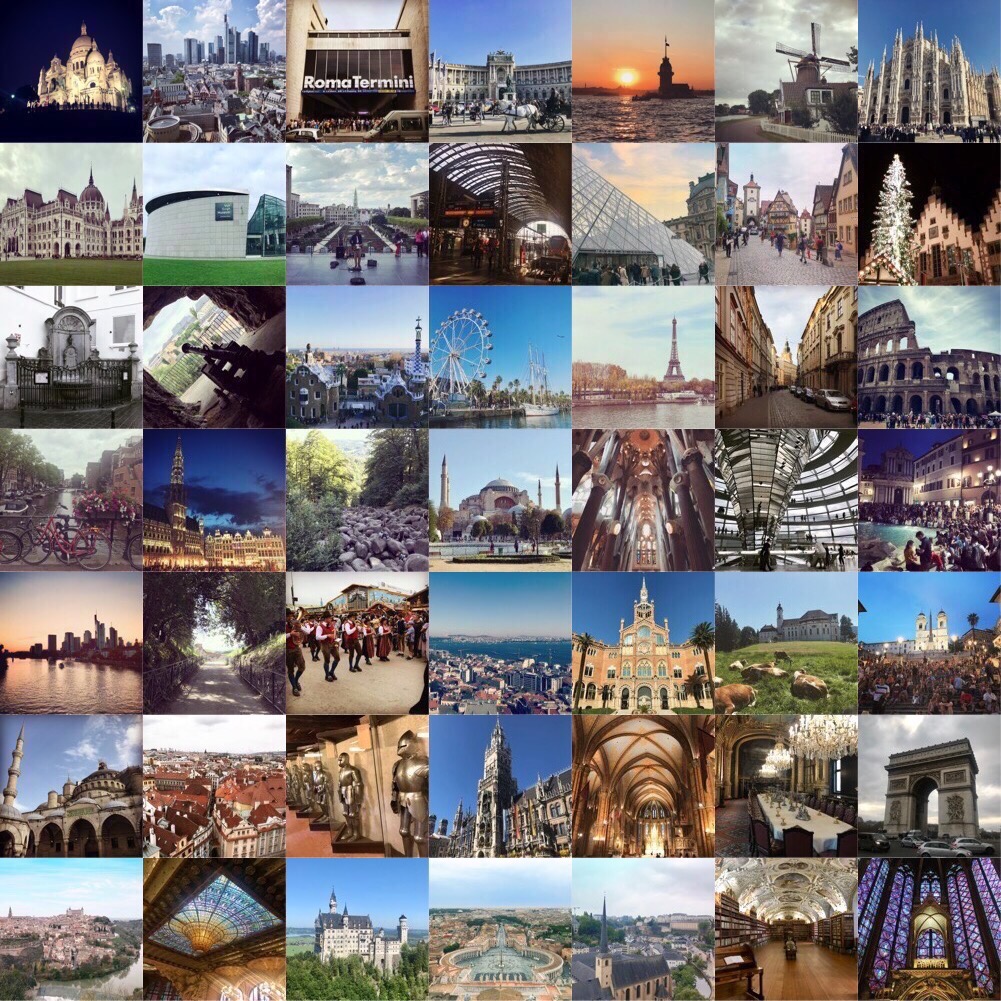
ヨーロッパ約20都市の旅行写真
コースが将来計画にどう役立ったか
初めは漠然とグローバルに活躍する人材になりたいという気持ちから海外インターンに参加し、その後もコースの科目を多く受講してきました。
今では日本人だけでなく多国籍チームで働くことの強みを理解し、実際にそんな環境で働けるスキルも身につけられたと思います。
自分のキャリアプランについては、海外での就職まで視野に入れると選択肢は莫大にあり、正直、将来自分がどこでどんな仕事をしているか想像できません。
ひとつ言えることは、グローバルに生きるということは同時に日本を客観視することでもあり、日本の良いところ悪いところが見えてきます。そういった視野の広がりがコースで得られたものであって、将来どこででも生きていけるという自信だけでなく日本で働くモチベーションもくれたと思っています。
最後に
正直な話、「ドイツに半年間いきました」と言うだけで「すごいね」とはなりませんし、留学に行ったからといって就職活動が余裕になるということも絶対ありません。
結局現地でどんなことを感じて、そこでどんな行動を取ったのかというその人自身のストーリーが大切だと思います。
近年では留学に行くこと自体は特別なことではないし、英語が話せるだけでもあまり珍しい人材ではありません。しかし、東工大で得られた専門性の高い知識にプラスして、英語や〇〇語が話せて、なおかつ海外で何か特別な経験をした視野の広い学生は絶対に貴重な人材です。もしこの記事を読んでいて、海外経験を積みたいと少しでも考えている方がいたら迷わず行ってこいと言いたいです。
今年は新型コロナウイルスの影響で海外に行きたくても行けなかった人たちがたくさんいると思います。留学支援をしているグローバル理工人育成コースのスタッフの方々も、この事態に頭を悩ませつつ、オンラインを使った様々な策を考えてくださっているそうです。少しでも国際的な活動に興味があったら、まずはコースにメール(ghrd.info@jim.titech.ac.jp)するか、実際に事務室(TakiプラザB1)に足を運んでみるのがいいと思います。実際に足を運ぶとスタッフの方々が親切に相談にも乗ってくれて、ときには雑談も付き合ってくれます。ある意味、大学っぽくない温かい雰囲気がありますよ。
最後に、私の話をもっと聞いてみたい方がいればLinkedInの方にコンタクトしていただければと思います。